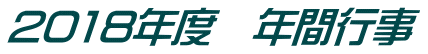
| *友の会ニュース発行 | *歴博歴史の旅 | *会員による会員のための見学会 | お申込み 各行事への参加申し込み 問い合わせはこちらへ |
| *会員のための講座 | *講演会 | *歴博映画の会 | |
| *自主学習会 | *新会員向けオリエンテーション | *観桜茶会 |
★ 友の会ニュース発行
| 発行年月 | 号数 | 発行予定日 | トップ記事他 | |
| 2018年(平成30年) | 4月 |
第196号 | 4月5日発行 | 2018年度活動方針、活動計画 特集展示「錦絵 in 1868」 特集展示「お化け暦と略縁起」 |
| 6月 |
第197号 | 6月5日発行 | 企画展示「ニッポンおみやげ博物誌」 ボランティア活動報告「喜ばれる寺子屋」をめざして 歴博をあるく「ミュージアム・ショップあれこれ」 |
|
| 8月 |
第198号 | 8月5日発行 | 歴博映像祭Ⅱ「民俗研究映像の30年」 友の会創立35周年記念講演会に向けて 自主学習会「日本の民俗を訪ねる」 |
|
| 10月 |
第199号 | 10月5日発行 | 企画展示「日本の中世文書 -機能と形と国際比較-」 特集展示「紀州徳川家伝来の楽器 -琵琶Ⅱ-」 第1展示室リニューアルの紹介 その1 |
|
| 12月 |
第200号 | 12月5日発行 | No.200記念特集号関連記事 特集展示「変わりゆく結婚式と近代化」 特集展示「吉祥のかたち」 第1展示室リニューアルの紹介 その2 |
|
| 2019年(平成31年) | 2月 |
第201号 | 2月5日発行 | 第1展示室リニューアルオープン 第1展示室リニューアルの紹介 その3 35周年記念講演会聴講報告 |
★ 歴博歴史の旅
| 宿泊を伴うちょっと遠出する歴史の旅です。年1回の2泊3日歴史の旅には歴博の先生も同行して解説をいただきます。歴博の先生から直接伺う、いつもより奥深い歴史にお酔いになりませんか。宿泊の宿では夕食後の勉強会もあります。 |  |
|||
| 実施年月日 | テーマ | 講師 | 備考 | |
| 2018年 | 11月11日(日) ~13日(火) |
南東北 戊辰戦争と震災の記憶 | 天野 真志先生 (専門:近世・近代史) |
|
★ 会員による会員のための見学会
| 半日、または1~2日の歴史見学会です。会員の皆さんの行ってみたいと思われる地をなるべく取り入れるようにしています。友の会会員が企画して、案内や解説も行います。毎回数10名の参加者が万歩計をともに歴史の思い出場所を散策します。ウォーキングを兼ねてあなたも参加してみませんか。 |  |
|||
| 実施年月日 | テーマ | 案内 | 備考 | |
| 2018年 | 5月12日(土) =>詳細 |
船橋(葛飾栗原郷)を歩く | 三橋 俊一 林田 秀孝 大野 吾一 |
春日神社、正延寺、勝間田公園、葛飾神社、宝成寺、葛羅の井、八坂神社 |
| 6月20日(水) =>詳細 |
両国界隈の歴史を訪ねる | 浅生 武治 小林 尚好 小池 裕 |
回向院、大高源吾の碑、吉良邸跡、勝海舟生誕の地、すみだ北斎美術館 | |
| 7月20日(金) =>詳細 |
霞ヶ浦沿岸をめぐる古代茨城バスの旅 (日帰りバス見学会) |
浅生 武治 渡邉 和男 神庭 恵 藤澤 晴子 野平 和男 |
横利根閘門、浮島(和田岬)、大杉神社、霞ヶ浦平和記念公園、上高津貝塚(ふるさと歴史の広場)、富士見塚古墳、牛久シャトー | |
| 9月13日(木) =>詳細 |
東上総(大多喜・いすみ)中近世バスの旅 (日帰りバス見学会) |
大野 吾一 三橋 俊一 鷲見 博史 谷中 直樹 |
大多喜城址、行元寺、万木城跡、海雄寺、メキシコ塔、ドン・ロドリゴ上陸の地 | |
| 10月26日(金) =>詳細 |
草加宿から草加松原を歩く | 鷲見 博史 小池 裕 谷中 直樹 |
浅古家地蔵堂、藤城家、草加市立歴史民俗資料館、東福寺、神明庵、神明宮、等 | |
| 2019年 | 1月14日(月) =>詳細 |
博物館初詣 「特別史跡・加曾利貝塚」を歩く |
浅生 武治 小林 尚好 鷲見 博史 林田 秀孝 |
北貝塚、南貝塚、大型建物跡・旧大須賀家住宅、加曾利貝塚博物館 |
| 3月9日(土) =>詳細 |
神楽坂から早稲田へ 武と学と文と芸のまちを歩く |
松本 博之 三橋 俊一 谷中 直樹 |
理科大近代科学資料館、見番、牛込城跡・天文方屋敷跡、紅葉旧居、杉田玄白生誕地、由井正雪屋敷跡、等 | |
★ 会員のための講座
| 歴博ガイダンスルームでおこなう歴博の先生による複数回の連続講座です。多くの会員が事前申込みのうえ参集しています。皆さんの興味のあるのはどの講座でしょうか。 |  |
| 古文書講座(入門コース) | 入門者のための古文書講座(上期、下期)、はじめて古文書を読もうとする方を対象にしたコースです (山本 光正先生) 上期:原則第2、第4水曜日、計10回(4月~9月) 下期:同上、計10回(10月~3月) |
||
| 古文書講座(Aコース) | 古文書をある程度の読める方が対象です。江戸時代の覚書や証文等の諸文書をとりあげ学習します(山本 光正先生) 上期:原則第2、第4火曜日、計10回(4月~9月) 下期:同上、計10回(10月~3月) |
||
| 古文書講座(Bコース) | 古文書をある程度の読める方が対象です。江戸時代の旅日記をテキストにして学習します (山本 光正先生) 上期:原則第1、第3水曜日、計10回(4月~9月) 下期:同上、計10回(10月~3月) |
||
| 歴史学講座 |
4月27日(金) 「奥羽の政治・文化と戊辰戦争」 (天野 真志先生) 5月 9日(水) 「聖徳太子の虚像と実像」 (仁藤 敦史先生) 6月21日(木) 「『延喜式』記載の地域特産食品から読み解く古代史」(仮) (清武 雄二先生) |
||
| 情報資料学講座 |
7月13日(金) 「年代測定あれこれ」 (坂本 稔先生) 8月 1日(水) 「歴史学とコンピューター」 (橋本 雄太先生) 9月27日(木) 「日本の色名と色材」 (島津 美子先生) |
||
| 考古学講座 |
10月 5日(金)「最終氷期に生きた人々」 (工藤 雄一郎先生) 11月 9日(金)「Bio-Archaeologyからみた縄文人の起源」 (山田 康弘先生) 12月21日(金)「リニューアル『水田稲作のはじまり』の みどころについて」 (藤尾 慎一郎先生) |
||
| 民俗学講座 |
1月 9日(水) 「産業遺産を残すことの意義と問題点 -林業を対象として-」 (柴崎 茂光先生) 2月 7日(木) 「近江商人の関東進出」 (青木 隆浩先生) 3月 7日(木) 「民俗学からみた老い」 (関沢 まゆみ先生) |
||
★ 講演会
| 友の会主催の歴博講演会です。歴博の先生や、たまには外部の先生から友の会会員に興味がありそうなテーマや先生方の最新の研究事例等の講演をいただいてております。 |  |
||
| 歴博館長特別講演会 | 「近世の道はきれいだったか」 講師:久留島 浩館長 |
2019年1月26日(土) |
|
| 恒例の館長特別講演会も今回で13回目を迎えます。館長の研究成果をお楽しみ下さい。 講演終了後、館長を囲んでの懇親会も予定しています。 場所:国立歴史民俗博物館 講堂 入場無料・申込不要(260名、先着順)(友の会会員以外の方も参加いただけます) 懇親会: 懇親会会場 歴博内 レストラン「さくら」 16:00~17:30 当日受付 会費 2,000円 問い合わせ:国立歴史民俗博物館友の会 電話043-486-8011 E-mail tomonokai@rekishin.or.jp |
|||
★ 歴博映画の会
| 歴博が制作および収集してきた記録映画を通じて民俗と歴史への知識と理解を深めていただくと共に、歴博の研究活動を皆様に知っていただくための企画です(歴博主催、友の会協力事業)。歴博の先生による作品解説も行います。 | ||||
| 実施年月日 | テーマ | 解説 | 備考 | |
| 2018年 | 今年度は開催休止 | |||
★ 自主学習会
| 友の会会員が自発的に立ち上げた学習会です。初心者からベテランまでの数名から、数十名の会員がそれぞれの学習会に集い、ともに学習しています。ほとんどの学習会が月1回のペースで開催されています。 友の会会員ならどなたでも参加できます。興味のある学習会に参加しませんか。本格参加の前の見学もお受けしております。 |
 |
| 近世史読書会 | 毎月第1水曜日 13:30~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| 1月から、水本邦彦著『村 百姓たちの近世』を読んでいます。本書は70年代研究のトレンドであった一揆や村方騒動等は扱わず、村絵図などを素材にして、村の成立、掟、災害等を通じて江戸の村を考察し、改めて現在の社会と比較し、見つめ直す試みをしています。いま、村の見方は変わりつつあります。興味ある方はぜひご参加を! | |||||
| 近現代史読書会 | 毎月第3火曜日 13:30~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| 20名程のメンバーが持ち回りでテキストの各章を要約・補足説明、また参考文献の紹介、論点などを纏めて発表しています。その後、侃々諤々の議論百出となりますが、紳士ぞろいの楽しい読書会です。現在、中国近現代史に取り組んでいます。 | |||||
| 古代の東国探訪学習会 |
毎月第3木曜日 13:30~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| 2015年の3月の例会100回を期して、これまでの古代、東国の枠に縛られず自由に考古・歴史等の学習結果・自説等を持ち寄って、発表・討論。サロン的雰囲気で友人作り・史跡探訪・懇親会などを実施しています。 | |||||
| 古文書学習会 | 毎月第4金曜日 13:30~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| 古文書を解読し、その時代背景を考え、内容を発表しています。現在「福富家文書」を読んでいます。大森銀山(幕府直轄地)の支配下にあった石見国福光下村の庄屋福富家の歴史を綴った地方文書です。武家文書と違い、癖のある字体ですが、知恵を絞りながら読み進めています。ご興味ある方は見学においでください。 | |||||
| 日本の民俗を訪ねる |
毎月第2水曜日 13:30~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| ジャワを代表する伝統音楽といえば「ガムラン」だが、佐倉市のDIC美術館で聴く機会があった。あの独特の楽器編成から紡ぎだされる調べに、なぜか遥か遠いニライカナイの波間に浮かぶヤシの実が「海上の道」を琉球から日本へと向って来るのが見えた。 | |||||
| 旅と街道学習会 |
毎月第4水曜日 13:30~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| 参勤交代や物資の輸送、信仰や物見遊山の旅等、近世には多くの街道が賑わい、今の街道の礎ともなっています。当会はこれら房総や近郊の街道を選び、街道の歴史や役割、地理、民俗等について図書館や現地を訪ね調査・発表しあいます。現在、東海道・水戸街道・国道51号・日光東往還を対象に多くの仲間と楽しく旅しています。 | |||||
| 総合展示物学習会 |
毎月第4木曜日 13:30~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| 歴史好きな私達にとって展示室内は歴史ロマンの詰まった宝庫です。展示物の関連資料を読み解きながら情報交換をし、日本の歴史(生活史)を学習しています。そして学習したことを展示室で確認し、知り得たことは共有している楽しい学習会です。 | |||||
| 日本の原始・古代を考える |
毎月第2木曜日 13:00~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| 謎の多い日本の原始古代(旧石器時代~平安時代)の実像は…? 「歴史とは…現在と過去との間の尽きることのない対話である」というE.H.カーの言葉を念頭に、各自が学習した内容を発表し、お互いの疑問点の解明を通して多様な意見の交換を行っています。 | |||||
| 日本の中世を探求する | 毎月第3金曜日 13:30~ 場所:国立歴史民俗博物館内会議室等 | ||||
| 2018年6月に発足したばかりの学習会です。15名ほどの参加者で、「中世とは何か」を課題図書の読み合わせと、各自が関心のある事項の発表とで、それを探求しています。問題は史料・学術の用語の意味です。国語辞典が中世史を学ぶには必要不可欠です。まずは「下文」から。…… | |||||
★ 新会員向けオリエンテーション
| 歴博友の会では、新会員の皆様が友の会活動を通して生涯学習の場にスムースに入れるよう、お手伝いをさせていただければと考え、新会員向けオリエンテーションを実施しています。新会員の皆様には、個別にご案内を差し上げますので、どうぞご活用ください。 | ||||
| 実施年月日 | 実施内容 | 場所 | 備考 | |
| 2019年 | 2月22日(金) |
第22回 新会員向けオリエンテーション |
13:30~15:30 国立歴史民俗博物館内 |
6月、10月、2月の3回を予定 |
★ 2018年度 観桜茶会
| 2018年4月8日(日) 10:00~15:00 (4月7日(土)天候不良のため8日に順延しました) 毎年恒例の観桜茶会、桜満開の佐倉城址公園での一服をお楽しみいただきました。 |
 |



