| 歴博歴史の旅 | 会員による会員のための見学会 | ||||||
| 5 月 | 6 月 | 9 月 | 11月 | 1 月 | 3 月 | ||
| 実施年月日 | テーマ | 講 師 | |
| 2024年度は中止します。 | |||
| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |
| 2024年 | 5月9日(木) | 国史跡「龍角寺古墳群・岩屋古墳」を歩く | 参加:26名 |
| 今回の見学地は印旛沼北東の台地上にある「龍角寺古墳群」で、その規模は前方後円墳37基、円墳37基、方墳6基、計115基を有する。年代は古墳時代後期から終末期にかけて築造されている。最初の「岩屋古墳」は日本最大級の方墳で、横穴式石室の入口柱には木下貝層の貝化石砂岩が使われており、地方色豊かな古墳である。 101号墳は龍角寺古墳群の中で最大の墳丘径25mの円墳で、8人の埋葬や埴輪の多さが際立っていた。また、古代工法と現代工法での円墳製造比較(大林組試算)では、工期で3倍、費用で15倍近くを有するころから、当時の権力者の財力を含め、権力の偉大さを感じさせるものであった。 風土記の丘資料館には、浅間山古墳の筑波石(雲母片岩)で構築された石室複製模型や龍角寺の資料などの展示があり、狭い資料館ではあるが、見どころの多い資料館であった。 浅間山古墳は古墳群の中で最大の前方後円墳で、現在後円部に浅間神社が祀られている。残念ながら樹木が生茂り全容確認が難しかった。 |
|||
| コース | 岩屋古墳→坂田ヶ池堤防→101号墳→古墳群遊歩道→風土記の丘資料館→古墳の広場→浅間山古墳→房総のむら入口 | ||
| 集 合 | 風土記の丘 岩屋古墳・石室前 13:30 | 解 散 | 房総の村入り口 16:00 |
| 案内会員 | 大野 吾一、三橋 俊一、浅生 武治、野平 和男 | 参加費 | 500円 |
 岩屋古墳にて説明を聞く |
 岩屋古墳横穴式石室入口 |
 101号古墳 |
 房総風土記の丘資料館前での説明 |
 房総のむら敷地内の旧学習院初等科正堂 |
 風土記の丘資料館 |
 古墳広場 |
 浅間山古墳後円部の浅間神社を望む |
| コース | JR飯田橋西口改札 → 牛込見附 → 外堀公園 → 市ヶ谷見附 → 四谷見附 → 聖イグナチオ協会 → 喰違見附 → 紀尾井坂 → 清水谷公園 → 弁慶橋 → 旧赤坂プリンスホテル → 赤坂見附 (現地解散) | ||
| 集 合 | JR飯田橋駅西口改札口(新宿寄り) 13:00集合 |
解 散 | 赤坂見附 16:00 |
| 案内会員 | 林田 秀孝、三橋 俊一、浅生 武治 | 参加費 | 500円 |
 牛込門跡 |
 阿波守内の石垣石の説明を聞く |
 雙葉学園前にて |
 JR四ツ谷駅地下展示 (江戸城外堀史跡展示広場) |
 喰違木戸門跡の説明を聞く |
 井伊家中屋敷跡 |
 紀尾井ホール |
 清水谷 |
 旧赤坂プリンスホテルのレストラン前で集合写真 |
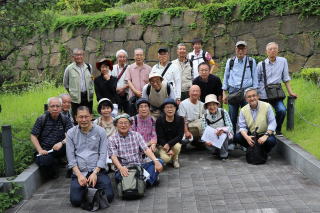 赤坂見附での記念写真 |
| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |
| 2024年 | 9月20日(金) | 市原の古代(3世紀から8世紀)を歩く | 参加:22名 |
| 快晴で熱中症アラートが発生する中、2グループに分かれバスで最初の目的地である南田瓦窯跡に向った。上総国分寺の建て替え用の瓦だと大量生産になるので、登り窯かなと思ったが、説明によると有畔式平窯4基の他、粘土の採掘跡や貯蔵庫もあったそうだ。次の見学地神門5号墳は、隣の路地にあった。神門には1,2がなく、3,4,5古墳群があるのだが、築造順は古い方から5,4,3の順で、4,3号墳は現在消滅している。各古墳共、鉄剣、鉄槍、鉄鏃などの出土品があり、4号墳の出土品は歴博2室古墳のコーナーに展示されている。 汗を流し、水分を補給しながら辿り着いた国分寺、建立の詔の写本は国分尼寺資料館に展示されていたが、詳細を知りたい方は『日本史資料 古代』岩波書店や『続日本書紀2巻』東洋文庫などで確認できる。僧寺で出迎えてくれたのは、唯一現存する金剛力士像とは言え、阿形像は鎌倉時代後期、吽形像は江戸時代後期の作だそうだ。僧寺の特徴である七重塔の礎石は、心柱と四天柱の部分のみしか残されていないが、その大きさに心柱の太さと高さの議論がはじまった。事務局による「塩飴」で塩分を補給し、国分尼寺へ向かう。国分尼寺では説明員から僧寺と尼寺の違い、ジオラマによる尼寺の配置、復元した金堂の基壇と回廊の特徴や苦労話などを現地で聞き、市原歴史博物館へ向かう。途中の稲荷台1号墳には暑さのため立ち寄りを中止した。博物館では、館長自らが説明役をされ、『歴博友の会ニュース』235号「歴博を歩く」の中で紹介した「イノシシ形土製品」の現物を見ることができた。また、稲荷台1号墳で発掘された「王賜」銘鉄剣は歴博で窒素封入ケースに収められ一時第2展示室で公開されていたが、市原歴史博物館開設に合わせ返却されたことに、感謝の言葉を述べられた。本品は展示されている特別室で間近に見ることができた。その他、荒久遺跡出土の灰釉花文浄瓶や三島台遺跡の穏やかな表情の人面付土器など、楽しい博物館であった。 |
|||
| コース | 五井駅東口バス停 ⇒ 🚌 ⇒ 国分時代中学校前 ⇒ 南田瓦窯跡 ⇒ 神門5号墳 ⇒ 国分僧寺跡 ⇒ 国分尼寺跡・資料館 ⇒ 市原歴史博物館 ⇒ 🚌 ⇒ 五井駅(解散) | ||
| 集 合 | JR内房線 五井駅改札口 12:40 | 解 散 | JR五井駅 16:50 |
| 案内会員 | 鷲見 博史、谷中 直樹、小池 裕、 長尾 純男 |
参加費 | 700円 |
 南田瓦窯跡の説明を聞く |
 神門5号墳 |
 神門5号墳の説明を聞く |
 上総国分寺石碑 |
 仁王門前 |
 将門塔(上総国分寺宝篋印塔) |
 国分僧寺の説明を聞く |
 七重の塔跡地 |
 国分尼寺跡の外観 |
 市原歴史博物館にて館長説明を聞く |
| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | |
| 2024年 | 11月12日(火) | 神宮外苑・青山霊園から乃木坂 | 参加:25名 |
| 今回の見学会は一人の欠席者も無く、好天に恵まれた見学会であった。聖徳記念絵画館は明治天皇の生涯を80枚の壁画にした、見ごたえのある展示物であった。明治神宮外苑のイチョウ並木は、先端部から黄葉がはじまっていた。青山通りから梅窓院不老門までの間は、金明竹の林になっており、青山家の菩提寺でもある。この青山の地名は旗本から大名に出世した、青山忠成の下屋敷に基づくものだそうだ。その一角の青山霊園には、大きな面積を所有する大久保利通の墓や、忠犬ハチ公の小さな祠、佐倉に関係のある津田仙の墓などがあった。乃木神社に隣接する旧乃木邸の中には入れなかったが、十分楽しめた見学会であった。 | |||
| コース | JR信濃町駅 → 聖徳記念絵画館 → 樺太日露国境天測標(レプリカ) → 御鷹之松 → イチョウ並木 (御観兵榎)・(明治神宮外苑之記碑)→ 梅窓院(青山通り)→ 青山霊園 → 旧乃木邸 → 乃木神社 |
||
| 集 合 | JR中央線信濃町駅改札口 13:00 | 解 散 | 地下鉄乃木坂駅 16:20 |
| 案内会員 | 谷中 直樹、林田 秀孝、浅生 武治 | 参加費 | 800円(入館料400円を含む) |
 JR信濃町駅に集合 |
 聖徳記念絵画館 |
 絵画館前にて記念撮影 |
 色づき始めた銀杏並木 |
 梅窓院にて説明を聞く |
 青山霊園に眠る津田仙の墓 |
 青山霊園に祀られる忠犬ハチ公の碑 |
 乃木神社 |
| 実施年月日 | 見学会名 | 備考 | ||
| 2025年 | 1月28日(火) | 江戸城三十六見附を歩く第2弾 日比谷見附から竹橋見附へ |
参加:28名 |
|
| 事前キャンセルや当日欠席者も無く、穏やかな日差しのもと、珍しく大群のスズメが合唱する中、見学会は始まった。配布された地図は見附の高麗門・渡櫓門や大番所(番所)が示さてれていて利用の頻度の高い資料であった。途中には江戸の行政をも受け持つ、南町奉行所跡(有楽町駅前)・北町奉行所跡があり、江戸は寺社奉行・勘定奉行・町奉行の3奉行体制で運営されているとの解説があった。また、参加者の案内で江戸城の保存石垣なども見ることができた。常磐橋見附の脇に建つ渋沢栄一は、明治の財界を盛り上げた人として新1万円札の顔となっているが、『徳川慶喜公伝』東洋文庫(平凡社)を出筆した文人でもあった。商人の財力により、日本橋商人町と神田職人町の間につくられた竜閑川は、日本橋界隈の商店の発達に寄与したことが伺える。また、江戸城築城の荷揚げ場所である鎌倉河岸も見逃せない所と言えよう。高層ビル群が立ち並ぶ大都会の中で、江戸時代の遺跡がこんなにも多く残っていることに感動した見学会であった。 余談だが『3か月でマスターする江戸時代』がNHKeテレで放映されている。このテキストの放送予定日程の頁に、御門の築城時期の小さな絵が掲載されている。また、歴博名誉教授横山百合子先生が、3月5日(水)の解説者として出演されることを、お知らせしておきます。 |
||||
| コース | 日比谷見附 → 数寄屋橋見附 → 南町奉行所 → 鍛冶橋見附 → 北町奉行所 → 呉服橋見附 → 常盤橋見附 → 神田橋見附 → 一ツ橋見附 → 雉子橋見附 → 竹橋見附 | ||
| 集 合 | 地下鉄日比谷線・千代田線・三田線 日比谷駅A10出口を上がった所 (日比谷公園前) 13:00 |
解 散 | 竹橋見附 16:00 |
| 案内会員 | 林田 秀孝、三橋 俊一、小池 裕、 谷中 直樹 |
参加費 | 500円 |
 スズメの合唱で見学会開始 |
 先ずは、日比谷見附で記念写真 |
 南町奉行所跡が有楽町駅前に |
 鍛冶橋見附で説明を聞く |
 常盤橋見附の渋沢栄一像 |
 常盤橋見附の日銀を背に記念写真 |
 常盤橋見附の遺跡の石垣 |
 神田橋見附 |
 一橋見附の遺跡の石垣 |
 一橋見附の前で説明を聞く |
 外堀の石垣 |
 最後に竹橋見附で解散 |
| コース | 銚子駅 → 妙福寺(紀國人移住碑)→ 濱口悟陵の碑(濱口家7代目)→ 仲の町駅 🚆 外川駅 → 外川漁港(千騎ヶ岩) → 崎山治郎右衛門碑(築港の祖・街並造成) → 大杉神社 → 銚子石採石場跡 → 長九郎稲荷(宝満・長崎海岸)→ 外川駅 🚆 観音駅 → 高崎藩陣屋跡 →(各自昼食)→ 飯沼観音 → 銚港神社🚌 川口神社 →千人塚 🚌 銚子駅(解散) | ||
| 集 合 | JR銚子駅 9:15 | 解 散 | JR銚子駅 15:30 |
| 案内会員 | 大野 吾一、鷲見 博史、野平 和男、 加瀬 良一 |
参加費 | 500円 ※別途、市内電鉄バス乗り放題 1,000円と昼食代を要します。 |
 妙福寺 |
 紀國人移住碑 |
 銚子電鉄 澪つくし号 |
 外川駅にて説明を聞く |
 千騎ヶ岩 |
 大杉神社 |
 長九郎稲荷神社の鯛とサンマと鰯の鳥居 |
 飯沼観音鐘楼門 |
 飯沼観音五重塔 |
 川口神社の説明を聞く |
